「沖縄でマイホームを建てるなら、やっぱりRC造(鉄筋コンクリート造)が安心だ」。そうお考えの方は多いのではないでしょうか。台風やシロアリに強く、がっしりとしたRC造は、沖縄の気候風土に適した選択肢の一つです。
しかし、そのRC造で「高気密高断熱」の高性能住宅を建てようと考え始めると、途端に情報が少なくなり、こんな悩みに直面しませんか?
- 沖縄のRC造・高気密高断熱をうたう会社は多いけど、本当に快適な家が建つのだろうか
- RC造は熱がこもりやすく、沖縄の夏では「夜も暑い家」になると聞いたけど本当?
- 「高気密」と言うけれど、ちゃんと気密測定(C値測定)をして性能を証明してくれる会社はあるの?
- 高性能にすると、結局木造と比べてどのくらい高くなるの?価格に見合う価値はある?
- ネットの情報だけでは、どのハウスメーカーや工務店を信じていいのか判断できない
今回は、そんなお悩みについて、私自身の家づくりの経験と徹底的な調査を基に考えていきます。
結論からいうと、沖縄でRC造の高気密高断熱住宅を建てること自体は可能ですが、ハウスメーカーや工務店の「性能への姿勢」を正しく見極めなければ、後悔する可能性が非常に高いです。
なぜなら、多くの会社が住宅性能の客観的な指標である「気密測定(C値測定)」を実施しておらず、性能がブラックボックス化している現実があるからです。
「でも、『RC造はそもそも構造的に気密性が高いから、測定しなくても大丈夫』って聞きますよ」
という声が聞こえてきそうです。
たしかに、コンクリートという素材自体は空気を通しにくく、気密性が高いのは事実です。しかし、建物全体の気密性能は、壁そのものよりも、窓やサッシの取り付け精度、配管が壁を貫通する部分の処理といった、細かな「施工精度」に大きく左右されます。
その施工精度を証明する客観的なデータがないまま契約を進めるのは、性能を運任せにするようなもので、大きなリスクが伴うと私は考えています。
この記事では、実際に高性能な木造住宅を建てた施主である私ぱんちょが、「もし今、RC造で家を建てるなら」という視点で徹底的に調べた情報をお届けします。
この記事を読むと以下のことが分かります。
- 沖縄のRC造・高気密高断熱住宅が抱える「理想と現実」
- RC造と木造のリアルなコスト比較と、それでもRC造を選ぶ価値
- 後悔しないハウスメーカー選びのための具体的なチェックポイント
RC造か木造か、どちらかが絶対的に正しいという話ではありません。この記事が、あなたが沖縄で本当に納得できる家づくりを進めるための、公平で信頼できる判断材料となれば幸いです。
「沖縄のRC造・高気密高断熱」は施工精度が鍵!その理由はC値測定の実態にある
- 沖縄でなぜコンクリートの家が主流?台風だけじゃないRC造の特徴とは
- 私も悩んだRC造の「高気密」という言葉の罠。本当に隙間はないのか?
- 【衝撃の事実】沖縄のRC住宅会社はC値測定をほぼ実施していない現実
- RC構造の蓄熱性が沖縄の気候にどう影響するか?「夜も暑い家」になる可能性
- 沖縄でRC造の高気密高断熱住宅をうたう主要ハウスメーカー4選
- 各社の断熱・換気仕様を比較!性能値(C値・UA値)は公開されているのか?
沖縄でなぜコンクリートの家が主流?台風だけじゃないRC造の特徴とは
沖縄の街を歩くと、ほとんどの家がコンクリートでできていることに気づきます。それもそのはず、データによれば沖縄県内の住宅のうち、実に約87.9%がRC造(鉄筋コンクリート造)で占められているという情報があります。これは全国のRC造比率である約5%と比べると、驚異的な数字です。
では、なぜ沖縄ではこれほどまでにコンクリートの家が選ばれるのでしょうか。
多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、やはり「台風への強さ」でしょう。毎年のように強力な台風が襲来する沖縄において、風雨に耐える堅牢な構造は、家に住む家族の命と財産を守るための必然の選択と言えます。
しかし、RC造が持つメリットはそれだけではありません。
RC造の主なメリット
- 耐火性: コンクリートは不燃材料であり、万が一の火災の際にも燃え広がりにくく、建物の倒壊までの時間を稼ぐことができます。これにより、家族が安全に避難する時間を確保しやすくなります。
- 耐久性: 法定耐用年数を見ても、木造の22年に対し、RC造は47年と倍以上です。適切なメンテナンスを行えば、文字通り100年住み続けることも可能な、非常に寿命の長い構造です。
- 防音性: コンクリートの壁は密度が高く、音を伝えにくい性質があります。車の通行音や近隣の生活音といった外部の騒音をシャットアウトし、静かでプライベートな空間を保ちやすいのも大きな特徴です。
このように、RC造は台風対策という側面だけでなく、防災、耐久、快適性という複数の観点から、沖縄の暮らしに適した合理的な選択肢として長年支持されてきたのです。
私も悩んだRC造の「高気密」という言葉の罠。本当に隙間はないのか?
RC造が当たり前?
親世代や周りの声から「沖縄ならRC造が安心」という漠然としたイメージが定着している。
合理的な選択だった
台風、火災、騒音といった沖縄特有の課題を克服するための、長年の知恵と経験が背景にある。
家づくりを計画していた当時、私も「高気密高断熱」というキーワードには非常に惹かれていました。そして沖縄の住宅会社を調べる中で、あるRC造メーカーが「RCは気密性が高い」と謳っているのを目にしました。
正直なところ、最初は「なるほど、コンクリートの塊なのだから、木造よりも隙間がなくて当たり前だよな」と、何の疑問も持たずにその言葉を受け入れていました。
しかし、高性能住宅について深く学んでいくうちに、その考えが少し短絡的であることに気づかされたのです。
確かに、コンクリートの「壁そのもの」は、空気を通しにくく、素材レベルで見れば気密性は高いと言えます。問題は、家全体の気密性(C値という指標で表されます)は、壁以外の部分の施工精度に大きく左右されるという事実です。
具体的には、
- 窓や玄関ドアの取り付け部分
- 換気扇やエアコンの配管が壁を貫通する部分
- 基礎と壁、壁と屋根のつなぎ目
といった箇所です。どれだけ分厚いコンクリートの壁を作っても、これらの部分に数ミリの隙間が空いていれば、そこから空気はどんどん出入りしてしまいます。つまり、「RC造だから高気密」なのではなく、「高気密になるように、細部まで丁寧に施工されたRC造だから高気密」というのが正しいのです。
この事実に気づいた時、「高気密」という言葉を鵜呑みにするのではなく、その根拠となる施工方法や、性能を証明する客観的なデータを確認する必要がある、と強く感じました。これは、これから家を建てる皆さんにぜひ知っておいてほしい、重要なポイントです。
【衝撃の事実】沖縄のRC住宅会社はC値測定をほぼ実施していない現実
「RC造の気密性は施工精度で決まる」。この事実を理解した私が次に行ったのは、「では、その施工精度をどうやって確認すればいいのか?」という調査でした。
その答えが、「気密測定(C値測定)」です。
気密測定とは、専門の機械を使って実際に建てられた建物にどれくらいの隙間があるのかを計測し、「C値」という数値で客観的に示すものです。この数値が小さいほど、隙間が少なく高気密な家ということになります。
高性能な木造住宅を手掛ける工務店では、この気密測定を全棟で実施し、施主に性能報告書として提出することが今や当たり前になりつつあります。私も自身の家の建築中に測定に立ち会い、C値=0.4という非常に高い性能が確保されていることを目の当たりにしました。
そこで当然、「RC造の住宅会社も同じように測定しているのだろう」と考え、各社のウェブサイトや資料を徹底的に調べました。しかし、そこで衝撃の事実に直面します。
沖縄のRC造住宅会社で、気密測定を標準で実施し、その数値を公表している会社は、ほぼ見当たらなかったのです。
「高気密」とは謳っていても、その根拠となるC値が示されていない。これは施主にとって、家の性能が完全にブラックボックス化していることを意味します。車を買うときに燃費のデータを見ない人はいません。しかし、住宅業界、特に沖縄のRC造市場では、それに近いことがまかり通っているのが現状です。
これは決して、沖縄の住宅会社が技術的に劣っていると言いたいわけではありません。おそらく、これまで「RCは丈夫で当たり前」という文化の中で、C値のような細かい性能数値を求められることが少なかった、という業界特有の事情があるのでしょう。
しかし、これから省エネで快適な暮らしを本気で求めるのであれば、施主側が「C値はいくつですか?」「気密測定はしてもらえますか?」と声を上げ、業界全体の意識を変えていく必要があるのかもしれません。
RC構造の蓄熱性が沖縄の気候にどう影響するか?「夜も暑い家」になる可能性
RC造の家づくりを検討する上で、もう一つ知っておくべき重要な特性が「蓄熱性」です。蓄熱性とは、熱を蓄える能力のことで、コンクリートは木材に比べてこの性質が非常に高い素材です。
この蓄熱性は、冬の寒さが厳しい本土などでは、昼間の太陽熱や暖房の熱を壁に蓄え、夜にゆっくりと放出してくれるため、「室温が冷めにくい」というメリットとして働きます。
しかし、この特性が沖縄の気候、特に夏場においては、大きなデメリットに転じる可能性があるのです。
沖縄の強い日差しを一日中浴びたコンクリートの壁は、大量の熱を蓄え込みます。そして、日が落ちて外の気温が下がり始めても、壁に蓄えられた熱がじわじわと室内へ放出され続けるため、「夜になっても家の中が全然涼しくならない」という現象が起こり得ます。
これが、昔ながらの断熱が不十分なRC住宅で「夏は夜も蒸し暑い」「エアコンがなかなか効かない」と言われる大きな原因の一つです。
このデメリットを克服し、RC造で夏の快適性を実現するためには、「そもそも壁に熱を蓄えさせない」ための断熱設計が極めて重要になります。
重要な断熱設計のポイント
- 外断熱の採用: 建物の外側を断熱材で丸ごと覆う「外断熱」は、コンクリートの躯体に熱が伝わるのを根本から防ぐため、最も効果的な手法の一つです。
- 高性能な窓・サッシ: 家の中で最も熱の出入りが大きいのは窓です。日射を遮蔽する性能が高い「Low-E複層ガラス」や、熱を伝えにくい「樹脂サッシ」などを採用し、開口部からの熱の侵入を徹底的に防ぐ必要があります。
RC造の蓄熱性は、諸刃の剣です。適切な断熱設計と組み合わせることで初めて、その恩恵を享受できるということを、ぜひ覚えておいてください。
沖縄でRC造の高気密高断熱住宅をうたう主要ハウスメーカー4選

沖縄でRC造の高気密高断熱住宅を建てたいと考えたとき、どのような選択肢があるのでしょうか。ここでは、ウェブサイトなどで積極的に性能をアピールしており、比較検討の土台となる主要なハウスメーカー・工務店を4社ご紹介します。
ただし、先述の通り、性能値の公開状況や気密測定への姿勢は各社で異なります。あくまで「高気密高断熱を謳っている会社」として、客観的な視点でリストアップします。
| 会社名・ブランド | 特徴 |
|---|---|
| 百年住宅 RC-NEXT | 工場で生産するPC(プレキャストコンクリート)パネルを使うWPC工法が特徴。品質が安定しており、工期が短い。「木造住宅並みのコスト」と「35年保証」を強みに、コストパフォーマンスを重視する層にアピールしている。 |
| 株式会社RCワークス | 断熱材付きの型枠を用いる「RC-Z工法」という独自技術を持つ。コンクリート打設と断熱工事を同時に行うことで、高い施工精度と外断熱を実現している。デザイン性の高い注文住宅を得意とする。 |
| 株式会社りゅうせき建設(RC+) | BELS認証やZEH認定を積極的に取得し、省エネ性能の「見える化」に取り組んでいる。内断熱を基本とし、発泡ウレタン吹付や熱交換換気システム、調湿建材「エコカラット」などを組み合わせ、総合的な快適性を追求。 |
| アイムホーム株式会社 | 現場でコンクリートを打設する壁式構造を採用。RC造の施工実績が豊富で、沖縄県内での建築棟数も多い。気密性の高い構造と、沖縄の高温多湿な気候に合わせた換気・空気循環システムを標準で採用しているのが特徴。 |
これらの会社は、それぞれ異なる工法や強みを持っています。デザインの好みや予算感と合わせて、各社のウェブサイトやカタログで詳細を確認し、比較検討の第一歩とすることをおすすめします。
各社の断熱・換気仕様を比較!性能値(C値・UA値)は公開されているのか?
ハウスメーカーを選ぶ上で、デザインや価格はもちろん重要ですが、「高気密高断熱」を求めるのであれば、その性能を裏付ける具体的な仕様を比較することが不可欠です。
先ほど挙げた4社について、公開されている情報を基に「断熱」「換気」「性能値の公開状況」を比較してみました。
| 会社名・ブランド | 断熱仕様 | 換気システム | C値・UA値の公開状況 |
|---|---|---|---|
| 百年住宅 RC-NEXT | 吹付発泡ウレタンフォームなど(内断熱) | 24時間換気システム(方式は非公開) | C値: 0.6~0.8と公表 UA値: 非公開 |
| 株式会社RCワークス | RC-Z工法(外断熱) | 個別相談(詳細は非公開) | 非公開 |
| りゅうせき建設 (RC+) | 発泡ウレタン吹付断熱(内断熱) Low-e複層ガラス | ダクトレス熱交換換気システム | 非公開 (BELS・ZEH認証は取得) |
| アイムホーム株式会社 | 高断熱仕様(詳細は非公開) | 給気&排気システム(詳細は非公開) | 非公開 |
この表から見えてくるのは、非常に興味深い事実です。
まず、各社とも断熱や換気に独自の工夫を凝らしている一方で、その具体的な仕様(断熱材の種類や厚み、換気方式など)や、性能を示す客観的な数値(UA値)をウェブサイト上で明確に公開している会社はほとんどありません。
唯一、百年住宅がC値の目安を公表していますが、これも保証値ではなく、またUA値は非公開です。りゅうせき建設はBELSやZEHの認証を取得しているため、一定の省エネ基準を満たしていることは分かりますが、具体的な数値までは分かりません。
この状況は、やはり施主が性能を客観的に比較検討する上で、大きな壁となります。
これらの情報が公開されていないからといって、性能が低いと断定することはできません。しかし、高性能を本気で追求するなら、カタログやウェブサイトの情報だけで判断するのではなく、必ず個別の相談会や見積もりの段階で、「UA値はいくつですか?」「換気は第何種ですか?メーカーはどこですか?」といった具体的な質問をぶつけてみることが重要です。その質問に対して、誠実に、そして明確に回答してくれるかどうかが、その会社の性能への姿勢を見極める一つのバロメーターになるでしょう。
より詳しい情報を知りたい方は、各社の資料を取り寄せて比較検討してみることをお勧めします。
とはいえ、一社ずつ問い合わせるのは時間も手間もかかりますよね。私もそうでしたが、まずは自宅で簡単に複数の会社から情報収集できるサービスを利用して、「自分だけの比較表」を作ることから始めてみてはいかがでしょうか。
【無料】タウンライフ家づくりで
気になる会社の性能や費用をまとめて比較してみる
【PR】タウンライフ家づくり
沖縄のRC造・高気密高断熱は価格以上の価値あり!その理由は快適性と光熱費にある
- RC造はやはり高い?木造と比較したリアルな坪単価と「私が木造を選んだ本当の理由」
- それでもRC造の高断熱化を選ぶ価値。初期コスト増を上回る長期的なメリット
- 高気密高断熱住宅は沖縄の猛暑と湿気にどれだけ効果的か?データで見る冷房効率
- 後悔しないハウスメーカー選びのポイントは「性能の見える化」への姿勢
- 【まとめ】私がもし今RC造で建てるなら、この3つのポイントを必ず確認します
RC造はやはり高い?木造と比較したリアルな坪単価と「私が木造を選んだ本当の理由」

「RC造は高い⋯。」
これは家づくりを検討したことがある人なら、誰もが一度は耳にする言葉ではないでしょうか。そして、その認識は残念ながら、そして客観的なデータから見ても「事実」であると言わざるを得ません。
その事実を最も象徴するのが、りゅうぎん総合研究所が発表した衝撃的な調査結果です。2023年度、沖縄県内の一戸建て住宅の着工戸数において、ついに木造が1,722戸となり、RC造の1,368戸を上回る「歴史的な逆転現象」が起きたのです。
長年「RC王国」であった沖縄で、なぜこのような大きな地殻変動が起きているのでしょうか。同レポートは、その背景を「人件費や地価の高騰による住宅取得費の増加」と分析しています。つまり、RC造の価格が上昇し続ける中で、より安価な木造住宅に需要が流れているという、極めてシンプルな経済原理が働いているのです。
何を隠そう、私自身が最終的に木造住宅を選んだ最大の理由も、この大きな流れの中にある「予算の都合」でした。
2025年現在の沖縄県内における坪単価の目安を見てみても、そのコスト差は明らかです。
| 構造 | 坪単価の目安 |
|---|---|
| 木造住宅 | 約60万~80万円/坪 |
| RC造住宅 | 約120万~150万円/坪 |
※いずれも高気密高断熱仕様の場合の目安。設計や仕様により変動します。
例えば30坪の家を建てる場合、単純計算で木造なら1,800万~2,400万円、RC造なら3,600万~4,500万円と、建物本体価格だけで無視できない差が生まれます。初期費用として数百万、あるいは一千万円以上の差が出てくると、一般的なサラリーマン家庭にとっては非常に大きな決断となります。
ただし、ここで一つ、私の正直な感想をお伝えしたいと思います。それは、「高性能な木造住宅も、決して安くはない」ということです。
高気密高断熱を実現するために、断熱材の性能を上げ、高性能なサッシを入れ、気密施工を徹底し、熱交換型の換気システムを導入する…と仕様を突き詰めていくと、木造住宅の坪単価もどんどん上がっていきます。
結果として、私の家の坪単価も、一般的なローコスト木造住宅よりはかなり高くなりました。もちろんRC造よりは安く収まりましたが、その価格差は当初想像していたほど「圧倒的」なものではなかった、というのが実感です。
この経験と市場データから言えるのは、構造で単純に比較するのではなく、「どのレベルの性能を求めるのか」によって、コストは大きく変わるということです。そして、RC造の初期コストの高さだけを見て諦める前に、その価格差を埋めるだけの価値があるのかどうかを、冷静に検討してみる必要がある、ということです。
家づくりを考え始めると、どうしても建物のことばかりに目が行きがちですが、実はそれと同じくらい大切なのが「お金の計画」です。自分たちに合った予算を知ることで、無理なく理想の家づくりを進めることができます。
もし、お金のことで少しでも不安を感じているなら、一度お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみるのも一つの手ですよ。我が家も相談しましたが、客観的な視点でアドバイスをもらえて、頭の中がスッキリ整理されました。
【相談無料】保険チャンネルで、住宅ローンや教育資金の不安をプロに相談してみる
FPに相談して将来設計を立てましょう。
それでもRC造の高断熱化を選ぶ価値。初期コスト増を上回る長期的なメリット

初期コストが高いという事実を踏まえた上で、それでも「RC造で高気密高断熱」を目指すことには、そのコスト増を正当化できるだけの明確な価値が存在します。家づくりは、建てて終わりではありません。むしろ、そこから何十年と続く暮らしの質とコストを考える「長期的な視点」こそが重要です。
1. ランニングコスト(光熱費)の大幅な削減
最も分かりやすいメリットは、日々の光熱費です。
高気密高断熱住宅は、魔法瓶のように外の熱を遮断し、中の快適な空気を逃しません。これにより、エアコンの稼働効率が劇的に向上します。特に、一年を通して冷房や除湿が欠かせない沖縄においては、その恩恵は絶大です。月々の電気代が数千円、年間で数万円単位で安くなることも珍しくなく、30年、40年という長いスパンで見れば、初期コストの差を十分に回収できる可能性があります。
2. 圧倒的な快適性と、家族の健康
夏の寝苦しい夜や、冬の底冷えから解放され、一年中、家のどこにいても温度差の少ない快適な環境で過ごせる。
これは、日々の暮らしの質(QOL)を大きく向上させます。また、急激な温度変化によるヒートショックのリスクを低減したり、適切な換気計画によって結露やカビの発生を抑え、アレルギーなどの健康リスクを遠ざけたりと、家族の健康を守るという観点からも非常に価値が高いと言えます。
3. 建物の長寿命化と、資産価値の維持
高気密高断熱住宅は、壁内結露のリスクが低減されるため、構造体の劣化を防ぎ、建物を長持ちさせます。
RC造の元々の耐久性と組み合わせることで、まさに「100年住宅」が現実のものとなります。また、将来的に家を売却したり貸したりする場合でも、省エネ性能が高く快適な家は、市場で高く評価される傾向にあります。初期投資は、未来の「資産価値」への投資でもあるのです。
これらのメリットは、単なる「贅沢」ではありません。豊かな暮らしを送るための「賢い投資」と捉えることができます。初期コストの数字だけにとらわれず、こうした長期的なリターンを総合的に判断することが、後悔しない家づくりに繋がります。
高気密高断熱住宅は沖縄の猛暑と湿気にどれだけ効果的か?データで見る冷房効率
「高気密高断熱にすれば、光熱費が安くなって快適になる」
これは理論上は分かっていても、実際に沖縄のあの厳しい暑さの中で、どれほどの効果があるのか、なかなかイメージしにくいかもしれません。
そこで、私ぱんちょが得意とする「データ」の出番です。我が家は木造ですが、高気密高断熱(C値0.4、UA値0.66)という点では同じです。SwitchBotの温湿度計を使って、我が家の夏の室温変化を24時間記録したデータがあります。
ある真夏日の記録を見てみましょう。外の最高気温が33℃に達した日でも、2階の寝室に設置したエアコン1台を27℃設定で24時間つけっぱなしにするだけで、家全体の室温は26〜27℃台でほぼ一定に保たれていました。
特筆すべきは、エアコンが設置されていない1階のリビング、洗面所に至るまで、大きな温度差がなかったことです。これは、家全体が魔法瓶のように断熱され、気密性が高いために冷気が家中に均一に行き渡り、外からの熱の侵入を強力にブロックしている証拠です。
これがもし、断熱や気密が不十分な家であればどうなるでしょうか。
- エアコンをつけている部屋だけが冷え、一歩廊下に出ると熱気を感じる。
- エアコンを切ると、数十分で室温が急上昇してしまう。
- 日差しが当たる壁の近くは、もわっとした熱気を感じる。
このような状況では、各部屋でエアコンをフル稼働させなければならず、電気代は高騰し、快適性も損なわれます。
このデータから言えるのは、「正しく施工された高気密高断熱住宅は、沖縄の猛暑に対しても絶大な効果を発揮する」という事実です。RC造であっても、適切な断熱・気密施工が行われていれば、同様かそれ以上の効果が期待できます。夏の電気代の請求書を見るたびに、その投資の価値を実感できるはずです。
ちなみに、私が家じゅうに設置して愛用しているのが、このSwitchBotの温湿度計です。スマホでどこからでも温湿度がチェックできて、過去のデータもグラフで見れるので本当に便利ですよ。
後悔しないハウスメーカー選びのポイントは「性能の見える化」への姿勢
ここまで、沖縄におけるRC造・高気密高断熱住宅のリアルな実態、コスト、そしてメリットについて解説してきました。これらの情報を踏まえると、後悔しないハウスメーカーや工務店を選ぶための、本当に重要なポイントが見えてきます。
それは、デザインや価格、営業担当者の人柄といった要素ももちろん大切ですが、それ以上に「住宅性能をいかに真摯に考え、それを施主に分かりやすく『見える化』しようとしているか」という姿勢です。
りゅうぎん総合研究所のレポートが指摘するように、沖縄の住宅市場は「大きな転換期」を迎え、RC造を手掛ける会社も「生き残るには戦略の工夫が必要」な時代に突入しました。私は、その「戦略の工夫」こそが、性能の「見える化」だと考えています。
言葉だけなら何とでも言えます。「うちは高気密高断熱ですよ」と言うのは簡単です。しかし、その言葉の裏付けとなる客観的なデータや具体的な仕様を示そうとしないのであれば、その性能は信頼に値しないかもしれません。
これからハウスメーカーと話をする機会があれば、ぜひ以下のチェックリストを手に、担当者に質問をぶつけてみてください。
【ハウスメーカー選び・性能確認チェックリスト】
- 性能目標値は明確ですか?
- 「UA値(断熱性能)の目標はいくつですか?」
- 「C値(気密性能)の目標はいくつですか?」
- 気密測定は実施しますか?
- 「全棟で気密測定を実施していますか?」
- 「もし標準でなくても、オプションで実施することは可能ですか?費用はいくらですか?」
- 「測定結果は報告書としていただけますか?」
- 断熱仕様は具体的ですか?
- 「断熱材の種類、厚み、施工方法(外断熱 or 内断熱)を具体的に教えてください」
- 「窓やサッシのメーカー名、製品名、性能値を教えてください」
- 換気計画は明確ですか?
- 「換気システムは第何種換気(1種・3種など)ですか?」
- 「熱交換機能はありますか?メーカー名と製品名を教えてください」
これらの質問に対して、淀みなく、そして具体的な数値や製品名で答えてくれる会社。あるいは、もし分からない場合でも「確認して後日ご報告します」と誠実に対応してくれる会社。そうした会社こそが、性能に対して真摯に向き合っている、信頼できるパートナー候補と言えるでしょう。
比較検討のためには、まず複数の会社から情報を集めることが不可欠です。一括資料請求サービスなどを利用して、気になる数社に同じ質問を投げかけてみるのも、各社の姿勢を比較する上で非常に有効な手段です。
【まとめ】私がもし今RC造で建てるなら、この3つのポイントを必ず確認します
【沖縄RC住宅】後悔しないための知識、ちゃんと身についた?
記事の内容を振り返りながら、重要なポイントをクイズで確認してみましょう!
選択肢をクリック(タップ)すると答えと解説が開きます。
私が「RC造だから高気密」とは一概に言えない、と考える最も大きな理由は何でしたか?
RC造の「蓄熱性」が、沖縄の夏で『夜も暑い家』というデメリットになるのは、どんな状況の時でしたか?
2023年度の沖縄の住宅市場で起きた「歴史的な逆転現象」とは、具体的に何でしたか?
信頼できる会社を見極めるため、私が最も重要だと考える「性能の見える化」。そのための最も大切な質問は何でしたか?
この記事で明かした、我が家が最終的にRC造ではなく「木造住宅」を選んだ最大の理由は何でしたか?
沖縄のRC住宅、高気密高断熱…なんだか専門的な話が多くて、少し頭が疲れてしまったかもしれませんね。
でも、私がこの記事で一番伝えたかったのは、とてもシンプルなことです。
「情報が少ない沖縄の家づくりだからこそ、言葉のイメージだけで判断せず、その裏付けとなる性能をしっかり確認することが、後悔しないために何より大切ですよ」ということなんです。
私自身、家づくりを始めたころは、たくさんの情報に振り回されて、何が本当か分からなくなり、心細い思いをたくさんしました。「きっと、昔の私と同じように悩んでいる方がいるはずだ」という想いが、この記事を書く原動力になっています。
この記事を読んで、「じゃあRC造はダメなのか」と感じた方もいるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。素晴らしい技術を持ったRC住宅の会社さんもたくさんあります。
大切なのは、木造か、RCかという二者択一ではなく、ご自身の家族がどんな暮らしをしたいのか、そして、その暮らしを実現するために、どんな性能が必要なのかをじっくり考えることだと思います。
もし、この記事がその「考えるきっかけ」になれたのなら、とても嬉しいです。
- リビングの空間活用や家電選びで悩んでいる方は、テレビを置かずにプロジェクターを導入した体験談も参考になります。空間の広がりや大画面体験のリアルを知りたい方はぜひご覧ください。
≫テレビを置かないプロジェクター生活のリアル!メリット&後悔したこと
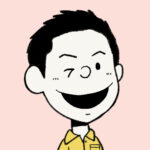
最後まで読んでいただきありがとうございます!
良かったら、感想や疑問、何でもコメント下さい♪



沖縄の建築情報が少ないのが難点!
LINEオープンチャットも開設しました!
お互いに情報交換しましょう☆


2022.05
\LINEのオープンチャット開設!/
沖縄でゼロから家づくりに悩んでいませんか?そんな方にとって情報収集&情報交換ができる場をつくりました!
【参加方法】
- スマホでQRコードを読み取る
- または、コチラから参加できます^^








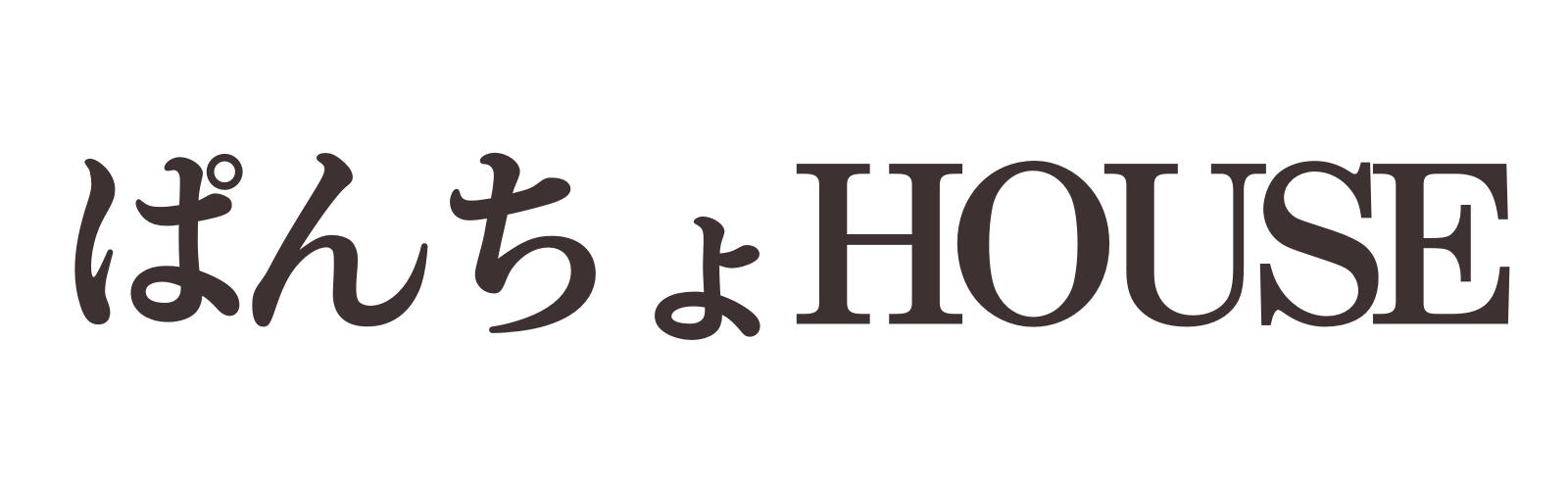



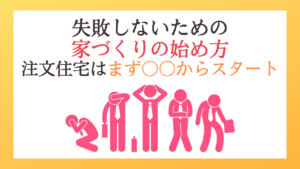





コメント