\こんなことで悩んでいませんか?/
- シーリングファンはおしゃれなだけで、 実用的な効果は無駄 なのではないか?
- エアコンの効率が上がると聞くけれど、ファンを回す 電気代で結局高くつく のではないか?
- 掃除が大変 で、すぐに使わなくなりそうだと心配している
- 天井が低い自宅に設置したら、 圧迫感があって後悔 しそうだ
- そもそも、 扇風機やサーキュレーターがあれば十分 なのではないか?
そのお悩み、そしてその疑問、私も家を建てる際に同じように感じていました。特に沖縄という高温多湿な環境で、いかに快適で省エネな暮らしを実現するかは、私にとって大きなテーマでした。
今回は、そんな私の実体験も交えながら、シーリングファンに関する疑問について、じっくりと考えていきたいと思います。
結論から言うと、 シーリングファンは「正しい知識」を持って「適切な環境」で使えば、決して無駄ではありません。
なぜなら、シーリングファンは室温そのものを変えるのではなく、空気全体を動かすことで、 エアコンが生み出した快適な空気を、部屋の隅々まで効率的に届ける役割 を果たしてくれるからです。
「でも、その理屈は分かっていても、掃除は面倒だし、本当に効果があるのか信じきれない…」
たしかに、その気持ちはよく分かります。特に、掃除の手間というデメリットは無視できません。しかし、そのデメリットを理解した上で、それを上回るメリットがあるのか、そして、どうすれば失敗や後悔を避けられるのかを知ることが重要です。
この記事を読むと、シーリングファンに関する以下の点が明確になります。
- シーリングファンが「無駄」と言われる本当の理由と、その効果を最大化する正しい使い方
- 具体的な電気代や、サーキュレーターとの明確な違い
- 私の「リアルな失敗談」から学ぶ、後悔しないための設置条件と注意点
単なる理想論ではなく、一人の施主として直面した現実も包み隠さずお話しします。この記事が、あなたの家づくりにおける後悔のない選択の一助となれば幸いです。
シーリングファンは無駄じゃない!理由は空気循環でエアコン効率を上げるから
- 正しい使い方をしないと逆効果?シーリングファンの本当の役割
- シーリングファンを24時間つけっぱなしにした電気代は「月800円台」が目安
- 冷房効率ならシーリングファン、スポット送風ならサーキュレーターが有利
- 夏は涼しく冬は暖かい!省エネ効果を高めるファンの正しい回転方向
- シーリングファンライトで後悔?照明としての明るさと機能の事前確認は必須
正しい使い方をしないと逆効果?シーリングファンの本当の役割
シーリングファンが「無駄だ」と感じられてしまう最も大きな原因は、その役割が正しく理解されていないことにあります。
大前提として、 シーリングファンはエアコンのように室温自体を下げたり上げたりする機械ではありません。 その本質は、大きな羽根で 「室内の空気をゆっくりと、かつ大きく循環させること」 にあります。
空気には、温度によって上下に移動する性質があります。
| 冷たい空気(冷房時) | 暖かい空気(暖房時) | |
|---|---|---|
| 性質 | 重く、下に溜まりやすい | 軽く、上に昇りやすい |
| 起こりがちな現象 | 足元だけが冷え、顔周りは暑い | 顔周りだけがのぼせ、足元は寒い |
この結果、同じ部屋の中でも「足元は冷えるのに、顔のあたりはモワッとする」といった不快な温度ムラが発生します。
シーリングファンは、この 温度ムラを解消する という重要な役割を果たしてくれます。
天井から床へ向けて、あるいは床から天井へ向けて穏やかな気流を作り出すことで部屋全体の空気を撹拌し、室内の温度を均一化。これにより、どこにいても快適な体感温度を得られるようになるのです。
エアコンとシーリングファンは、それぞれの役割を補い合う良いパートナーのような関係です。エアコンが生み出した快適な空気を、シーリングファンが部屋の隅々まで届ける。この連携によってはじめて、その効果をしっかり引き出すことができるのです。
逆に言えば、この役割を理解していないと、「なんだ、涼しくないじゃないか。無駄なものを付けた」という結論になってしまいがちです。シーリングファンは、それ自体が快適さを作り出すのではなく、 既にある快適さを空間全体に広げるための装置 なのです。
- シーリングファンは空気循環が重要な役割ですが、そもそも高気密高断熱住宅ではどのような効果が期待できるのでしょうか。沖縄で高気密高断熱住宅を建てた私の実体験と、なぜこの選択が正しかったのかを詳しく解説した記事があります。
≫ 【体験談】沖縄で高気密高断熱の家づくり。私が「これだ!」と確信した日
シーリングファンを24時間つけっぱなしにした電気代は「月800円台」が目安

「空気を循環させる効果は分かったけど、ずっと回しっぱなしだと電気代が心配…」
正直に告白すると、私自身、家を建てた当時はシーリングファンのモーターに種類があることなど全く知らず、デザインや価格だけで深く考えずに製品を選んでしまいました。製品に明確な記載がないため断言はできませんが、おそらく一般的な 「ACモーター」 の製品だと思われます。
そんな知識不足だった私ですが、後から調べてみると、モーターには大きく分けて「ACモーター」と「DCモーター」の2種類があり、消費電力にかなりの差があることが分かりました。
| モーターの種類 | 消費電力の目安(最大時) | 1時間の電気代 | 24時間つけっぱなしの電気代(1日) | 1ヶ月(30日)の電気代 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACモーター | 約40W | 約1.24円 | 約29.76円 | 約892.8円 | 本体価格が比較的安価。風量調節が大まかな製品が多い。 |
| DCモーター | 約20W | 約0.62円 | 約14.88円 | 約446.4円 | 本体価格は高めだが、消費電力が非常に低く省エネ。静音性が高く、細かな風量調節が可能。 |
表を見て分かる通り、我が家が使っているであろうACモーターの製品でも、24時間つけっぱなしの電気代は 1ヶ月で900円弱 。もし知識があって省エネ性能の高いDCモーターの製品を選んでいれば、その 半額程度の450円以下 に収まっていたかもしれません。これは少し後悔しているポイントです。
しかし、どちらのモーターであっても、ファンを回す電気代はエアコンの消費電力に比べればごくわずかです。環境省のデータによれば、夏にエアコンの設定温度を1℃高くするだけで約13%の節電効果があるとされています。
つまり、シーリングファンを回す数百円のコストは、エアコンの設定温度を緩和できることによる 節約効果で、十分に相殺できる 可能性が高いのです。
シーリングファンやエアコンの電気代を根本から見直すなら、電力会社のプランを一度比較してみるのも賢い選択です。我が家もそうですが、気づかないうちにもっとお得なプランが登場しているかもしれません。
\【無料】エネチェンジで最適な電気料金プランを調べてみる/
- シーリングファンの電気代について詳しく解説しましたが、家全体の電気代を考えると、高気密高断熱住宅の性能が大きな影響を与えます。我が家で実際に1年間記録した電気代の詳細データをまとめた記事がありますので、ぜひ参考にしてください。
≫ 沖縄の高気密高断熱住宅、電気代はいくら?!太陽光&全館空調1年間の記録
冷房効率ならシーリングファン、スポット送風ならサーキュレーターが有利
「空気の循環なら、サーキュレーターでいいのでは?」という疑問も、当然ながら浮上します。見た目もシンプルで価格も手頃なサーキュレーターは、確かに強力なライバルです。
シーリングファンとサーキュレーター、どちらが良いかは、 「どのような空気の流れを作りたいか」 によって決まります。両者の最も大きな違いは、 「風の質と範囲」 です。
| 項目 | シーリングファン | サーキュレーター |
|---|---|---|
| 得意なこと | 部屋全体の空気を 広く、穏やかに 撹拌・循環させる | 特定の方向へ 直線的で強い 風を送る |
| 風の質 | 面で捉えたような、ふんわりとした優しい風 | 直線的でパワフルな風 |
| 効果範囲 | 部屋全体 | 狙った場所(スポット) |
| 主な目的 | 室内の温度ムラ解消、体感温度の調整 | 部屋の隅への送風、洗濯物の乾燥、隣の部屋への送風 |
| 設置場所 | 天井(空間を占有しない) | 床や棚の上(スペースが必要) |
| デザイン性 | インテリア要素が高い | 機能性重視でシンプルなものが多い |
シーリングファンが向いているケース
リビングのような広い空間で、 部屋全体の温度ムラをなくし、どこにいても心地よい環境を作りたい のであれば、シーリングファンが最適です。天井から広範囲に穏やかな風を送るため、不快な風当たりを感じることなく、空間全体の快適性を高めることができます。
サーキュレーターが向いているケース
一方で、 エアコンの風が届きにくい部屋の隅や、壁の向こう側にある隣の部屋までピンポイントで風を送りたい 場合や、部屋干しの洗濯物を集中して乾かしたい場合には、直線的な強い風を送れるサーキュレーターが有利です。直進性の高いパワフルな風で遠くまでエネルギーを失わずに空気を送り届けることができます。
このように、両者は似ているようで得意なことが異なります。
空間全体の快適性を求めるならシーリングファン、特定の目的で力強い風が必要ならサーキュレーター、というように使い分けるのが賢明です。もちろん、両者を併用して、それぞれの長所を活かすという使い方も、もちろんアリです。
- シーリングファンとサーキュレーターの違いについて説明しましたが、特に部屋干しでの効果を詳しく比較した記事があります。洗濯物の乾燥という観点から見ると、どちらがより効果的なのかが分かります。
≫部屋干しには扇風機とサーキュレーター、どっちが効果的?最適な方法をまとめてみた
夏は涼しく冬は暖かい!省エネ効果を高めるファンの正しい回転方向

シーリングファンが一年を通して活躍できる、非常に重要な機能が 「回転方向の切り替え」 です。この機能を正しく使いこなすことで、夏はより涼しく、冬はより暖かく、快適な室内環境を作り出すことができます。
| 夏(冷房時) | 冬(暖房時) | |
|---|---|---|
| 回転方向 | 反時計回り (左回り) | 時計回り (右回り) |
| 風向き | 下向き の気流 | 上向き の気流 |
| 目的・効果 | 風を直接肌に当て、 体感温度を下げる (風速冷却効果) | 天井の暖気を循環させ、 足元の冷えを緩和する |
夏(冷房時)は「反時計回り」で涼しく
夏場は、ファンを 「反時計回り」 に設定します。下向きの気流が直接肌に当たることで涼しく感じられ、エアコンの設定温度を1〜2℃高くしても快適に過ごせます。
冬(暖房時)は「時計回り」で暖かく
冬場は、回転方向を 「時計回り」 に切り替えます。上向きの気流が天井の暖気を壁伝いに降ろし、部屋全体を均一に暖めます。直接風が当たらないので、寒さを感じることなく温度ムラだけを解消できます。
この回転方向の切り替えは、リモコンや本体のスイッチで簡単に行える製品がほとんどです。季節の変わり目に忘れずに行うだけで、年間の快適性と省エネ効果が大きく変わってくる、重要なポイントです。
シーリングファンライトで後悔?照明としての明るさと機能の事前確認は必須
シーリングファンを選ぶ際、多くの人が検討するのが「照明付き」のモデル、いわゆる シーリングファンライト です。ファンと照明が一体になっているため、天井がすっきりするメリットがありますが、一方で「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。
失敗を避けるためには、明るさ(適用畳数)や光の色(調色機能)、明るさの調整(調光機能)といった 「照明としての基本性能」 を事前にしっかり確認することが大前提となります。
【我が家の活用法】SwitchBotスマートライトで快適性が劇的に向上
我が家では、シーリングファンライトに元々付いていた電球を外し、代わりに 「SwitchBotのスマートLED電球」を4つ設置 しています。これが、想像以上に快適な暮らしに繋がりました。
具体的には、以下のような使い方をしています。
- グループ化で一括操作: 4つの電球をアプリで一つのグループに設定。「アレクサ、照明を消して」と声をかけるだけで、4つ同時に消灯・点灯できます。
- 音声での明るさ調整: 「アレクサ、リビングの照明を明るくして」「照明を暗くして」といった声かけで、簡単に明るさを調整しています。
- タイマー・自動化設定: アプリで「夜9時になったら自動で消灯する」「朝6時になったらゆっくり点灯する」といった設定も可能です。寝落ちしてしまっても電気が消えるので、非常に重宝しています。
このように、スマートライトを組み合わせることで、シーリングファンライトの利便性は劇的に向上します。ファン自体に高機能な照明が付いていなくても、後から自分でアップグレードできるというわけです。これは、シーリングファンライトを検討している方には、ぜひ知っておいてほしい活用術です。
我が家で実際に使っているのが、こちらのSwitchBotのスマートLED電球です。音声操作やタイマー設定ができるだけで、暮らしの快適さが格段に上がりました。
▼我が家で愛用中「SwitchBot スマートLED電球」の詳細はこちら
- シーリングファンライトにスマート機能を追加することで、より快適な暮らしが実現できます。我が家ではテレビを置かずにプロジェクターを採用しましたが、このような暮らしの工夫について詳しくまとめた記事があります。
≫テレビを置かないプロジェクター生活のリアル!メリット&後悔したこと
「シーリングファンが無駄」になる失敗例とは?理由は設置条件とデメリットの軽視
- シーリングファンの最大の欠点は「掃除の手間」!高所作業という現実
- 天井が低いと効果なし?わが家の「天井高2700mm」でのリアルな失敗例
- 【対策】圧迫感を避けるため「薄型のシーリングファン」を選んだのが現実解
- 意外と気になる運転音や振動。静音性を求めるならDCモーターがおすすめ
- 天井の強度不足はNG!購入前に必ず確認すべき設置条件
シーリングファンの最大の欠点は「掃除の手間」!高所作業という現実

ここまでシーリングファンのメリットを中心に解説してきましたが、物事には必ず裏表があります。私が考えるシーリングファンの 最大の欠点、それは紛れもなく「掃除の手間」 です。
これは綺麗ごとでは済まされない、非常に現実的な問題です。
シーリングファンの羽根は、空気を動かす過程で静電気が発生しやすく、部屋中のホコリを吸い寄せる磁石のような存在になります。しばらく放置すると、羽根の上にはうっすらと黒いホコリが積もっているのが見えるでしょう。
このホコリを放置したまま、例えば回転方向を冬仕様に切り替えたりすると、溜まったホコリが部屋中に舞い散る…なんていう悲劇も起こりかねません。
そして、何より大変なのが、その 掃除が「高所作業」になる という点です。ご家庭によってはしっかりとした脚立も必要になりますし、吹き抜けなら柄の長い専用モップがないとそもそも届きません。上を向きながら不安定な体勢で作業を行うのは、思った以上に大変です。
この掃除の手間を軽視して導入すると、「掃除が面倒だから、結局使わなくなった」という、まさに「無駄なもの」にしてしまう原因になり得ます。
導入を検討する際は、この掃除の手間を許容できるか、定期的に掃除をする覚悟があるかを、ご自身のライフスタイルと照らし合わせて冷静に判断することが大切になります。
天井が低いと効果なし?わが家の「天井高2700mm」でのリアルな失敗例
シーリングファンの効果を最大限に引き出すためには、 「設置条件」が極めて重要 になります。そして、この点において、私自身の家づくりには正直に言って「失敗」と認めざるを得ない部分があります。
シーリングファンが最も効果を発揮するのは、暖かい空気が上昇して温度ムラが大きくなりやすい「吹き抜け」や「高天井」のリビングです。理想を言えば、天井高は3m以上あるのが望ましいとされています。
我が家の場合、リビングの天井高は一般的な2400mmよりは高い 2700mm(2.7m) を確保しました。しかし、これは吹き抜けと呼べるほどの高さではありません。
さらに、設計上のアクセントとして天井に「見せ梁」を設けたのですが、これがシーリングファンの設置において大きな足かせとなってしまいました。ファンが効率よく空気を循環させるためには、 羽根の先端から壁や梁などの障害物まで、最低でも40cm〜50cmの距離を確保するのが理想 とされています。
しかし、我が家のシーリングファンと見せ梁との隙間は、 おそらく5cmもありません。
これは、空気の流れを著しく妨げる可能性があり、シーリングファンの性能を十分に引き出せていないことを意味します。なぜこうなってしまったか。それは、家づくりの計画段階で、私自身にそこまでの詳細な知識が不足しており、設計士との打ち合わせでもその点が十分に考慮されなかったからです。
このように、理想的な設置条件から外れてしまうと、せっかく導入したシーリングファンの効果が半減し、「あまり意味がない」「無駄だったかも」と感じてしまうリスクが高まります。これは、これから家を建てる方にはぜひ知っておいてほしい、私のリアルな反省点です。
【対策】圧迫感を避けるため「薄型のシーリングファン」を選んだのが現実解

先ほどお話しした通り、我が家のリビングは吹き抜けではなく、天井高も2700mmと、シーリングファンを設置するには「理想的」とは言えない条件でした。
このような状況で、もし一般的な厚みのあるシーリングファンを選んでいたら、天井からの圧迫感が強くなり、空間が狭く感じられたことでしょう。また、延長パイプを使ってファンを下に降ろす選択肢もありましたが、そうすると今度は頭上にファンが近づきすぎてしまい、これもまた圧迫感や安全性の観点から現実的ではありませんでした。
そこで我が家が選んだのが、 「薄型」と呼ばれるタイプのシーリングファン です。
薄型モデルは、その名の通り、本体の厚みが抑えられており、天井に張り付くように設置できるのが特徴です。天井から羽根までの距離を短くできるため、 我が家のような標準的な高さの天井でも圧迫感を最小限に抑えることができます。
もちろん、薄型にすることで空気循環の効率が多少犠牲になる側面は否めません。天井と羽根の間に十分な空間があった方が、より多くの空気を動かせるのは事実です。
しかし、「理想的な効果」を追求するあまり、日々の暮らしの中で「圧迫感」というストレスを感じ続けるのは本末転倒です。吹き抜けではない、ごく一般的な天井高の部屋にシーリングファンを導入したいと考える方にとって、この 「薄型モデル」を選ぶという選択は、デザイン性と実用性のバランスを取った、非常に有効な「現実解」 だと私は考えています。
▼我が家のように、天井の高さに制限があるけどシーリングファンを諦めたくない、という方には「薄型」のモデルが本当におすすめです。圧迫感なく空間に馴染む製品がたくさんありますよ。
意外と気になる運転音や振動。静音性を求めるならDCモーターがおすすめ
デメリットとして見落とされがちですが、 「運転音」や「振動」 も、日々の快適性を左右する重要な要素です。
正直なところ、我が家で使っている製品(おそらくACモーター)は、 家族が寝静まった深夜など、静かな環境では少し運転音が気になる ことがあります。「ブーン」という低いモーター音ですが、一度気になりだすと、なかなか頭から離れない方もいるかもしれません。
この実体験があるからこそ、もしこれからシーリングファンを購入する方がいるなら、私は 静音性に優れた「DCモーター」搭載モデルを強くおすすめします。
DCモーターは、ACモーターに比べて運転音が格段に静かです。さらに「微風」などの極めてゆっくりとした回転ができるため、風切り音もほとんど気になりません。寝室への設置を考えている方や、音に敏感な方であれば、その差は歴然と感じるはずです。
「でも、DCモーターの製品は高いんじゃ…」と思うかもしれませんが、最近では価格もこなれてきています。Amazonなどで調べてみると、 2万円前後からDCモーター搭載のシーリングファンライトが見つかります。
初期投資は少し高くなるかもしれませんが、毎日の快適性とストレスのなさを考えれば、その価値は十分にあると、ACモーターユーザーの私だからこそ感じる点です。
ACモーターの音を実際に体験しているからこそ、DCモーターの静音性の価値がよく分かります。特に寝室への設置を考えている方には、こちらのタイプを強く推奨します。
→Amazonで「2万円前後|静音性に優れたDCモーター搭載モデル」」を探す👀
→楽天市場の口コミで「DCモーターモデル」の静かさを確認してみる👀
天井の強度不足はNG!購入前に必ず確認すべき設置条件

最後に、デザインや性能以前の、 安全性に関わる最も重要な確認事項 についてです。それは「 天井の強度」 です。
シーリングファンは、軽量なモデルでも数kg、照明付きの大型モデルになると10kgを超える重量があります。この重さに、回転による遠心力が加わるわけですから、設置する天井には相応の強度が求められます。
もし、強度が不足している場所に無理やり取り付けてしまうと、 最悪の場合、運転中に本体が落下するという重大な事故 に繋がりかねません。
【我が家の場合】設置は工務店にお任せ
口コミなどを見ると、「重たくて一人での設置は大変だった」「取り付けに1時間以上かかった」といった声を見かけます。DIYでの設置も可能ですが、かなりの労力と専門知識、そして何より危険が伴います。
その点、 我が家では新築時に照明器具の一つとして、工務店さんに設置をお願いしました。 そのため、設置に関する苦労は一切ありませんでしたし、天井の補強も計画段階から織り込んでもらえたので、強度に関する心配もありません。
これから家を建てる方やリフォームをされる方は、このように専門の業者さんに設置を依頼するのが最も安全で確実です。もし、ご自身で購入した製品を取り付けてもらいたい場合は、「施主支給」という形で対応してもらえるか、事前に建築業者さんや工務店さんに確認してみることをおすすめします。
これから家づくりを始める方で「天井補強やシーリングファンの設置にも柔軟に対応してくれる工務店を探したい」という場合は、複数の会社から間取りプランやカタログを一度に取り寄せられるサービスで比較検討するのも一つの手です。
タウンライフ家づくりで理想の家づくりを相談してみる
【PR】タウンライフ家づくり
【まとめ】シーリングファンは「無駄」じゃない!ただし条件付き
「シーリングファンは無駄?」記事のまとめ確認クイズ
記事の内容を振り返りながら、重要なポイントをクイズで確認してみましょう!
選択肢をクリック(タップ)すると答えと解説が開きます。
シーリングファンが夏の冷房効率を上げる本当の理由は何でしょうか?
冬に暖房と併用する際、シーリングファンの効果的な回転方向と目的の組み合わせはどれでしょう?
私が「もし知っていれば…」と少し後悔している、静音性が高く省エネなモーターの種類は何だったでしょうか?
我が家がシーリングファンの性能を十分に引き出せていない「失敗点」とは、具体的に何だったでしょうか?
デザインや性能の前に、シーリングファンを安全に設置するために最も重要な確認事項は何でしょうか?
シーリングファン、いかがでしたでしょうか。なかなか奥が深い世界ですよね。
「無駄か、無駄じゃないか」という二者択一で考えると、きっと答えは出にくいのだと思います。大切なのは、シーリングファンという設備の「得意なこと」と「苦手なこと」をきちんと理解したうえで、ご自身の住環境や「どんな暮らしがしたいか」という想いに、それがフィットするかどうかを考えてみること。
今回、我が家のちょっとした失敗談まで正直にお話ししたのは、家づくりには「たら・れば」が付きものだからです。後から「ああすれば良かった!」と思うことは、大小さまざま、必ず出てきます。
完璧な家づくりを目指すのはもちろんですが、情報が少ない中で100点満点を取るのは至難の業。だからこそ、私のような一個人の、しかも少しばかり後悔している経験でも、これから家づくりをされる方の「しまった!」を一つでも減らせるなら、それに勝る喜びはないな、と感じています。
この記事が、「うちには吹き抜けがあるから相性が良さそう」「天井が低いから薄型モデルを検討しようかな」「いや、掃除の手間を考えると、うちはサーキュレーターが合ってるかも」…そんな風に、ご自身の暮らしに置き換えて考える、一つのきっかけになったなら、とても嬉しいです。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!








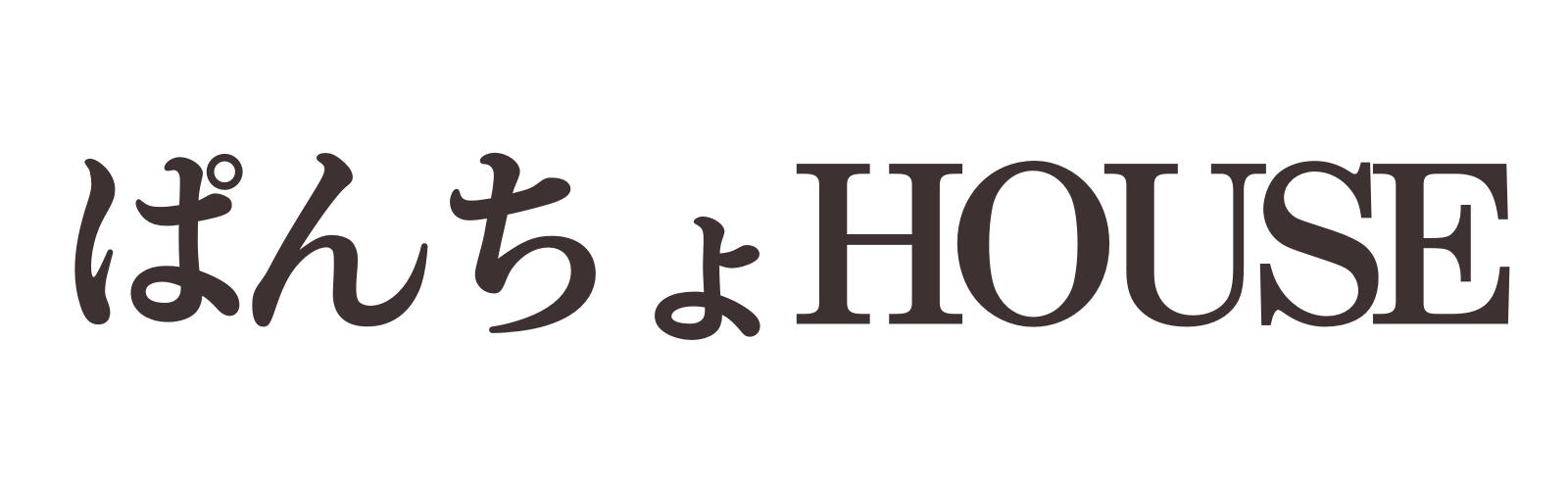








コメント